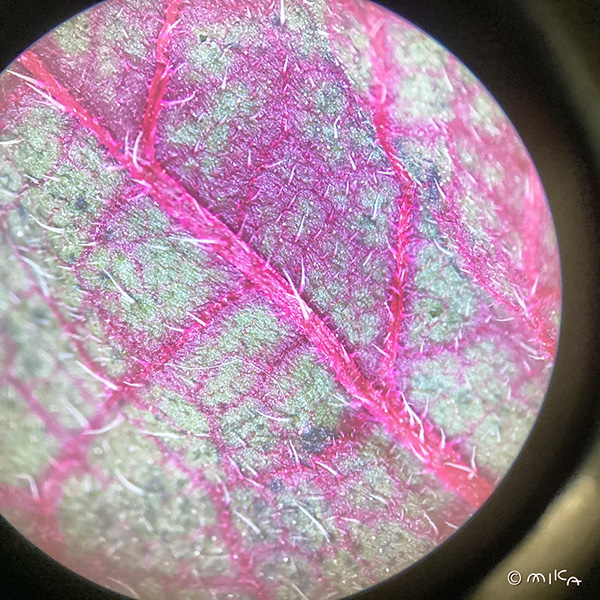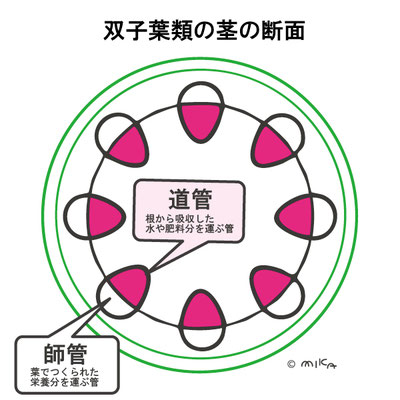- ホーム
- NEW
- ほっこりイラスト▼
- 季節の工作等▼
- ひと息 写真集▼
- 生き物図鑑▼
- 和みKANSAI▼
- 花と実図鑑▼
- 頭の体操
- 料理(ごはん)▼
- 月ごと絵手紙▼
ひまわり(sunflower)
ニコニコ 大輪
ヒマワリ(キク科)
・7~9月頃、真夏の太陽の下、日本全国で咲く 元気な花。明るい太陽を思わせる花の形から、英語でも sunflowerと呼ばれます。北アメリカ原産。
・1つの大きな花に見えますが、実は多数の花が集まって、1つの花を形成しています(頭状花序)
・タネは食用になり、油もとれます。
・花言葉は「あこがれ」「愛慕」など。
他にも様々な種類があります(順にビューティフルサン、パチノゴールド、パチノコーラ、パン、サンリッチミックス)
※このページのヒマワリの写真は、京都府立植物園、ひまわりの里まんのう(香川県中山ひまわり団地)、万博記念公園(大阪府)、あわじ花さじき、古宇利島(沖縄県)等にて撮影
※このページの説明は、各植物園や公園の解説、「植物(小学館)」「飼育・栽培(学研)」等より抜粋。
※ 下記は別ページがあります
※ サイト内検索
このウェブサイトでは、快適な閲覧のために Cookie を使用しています。閲覧を続けることで、 Cookie ポリシーに同意したことになります。
概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。
本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。