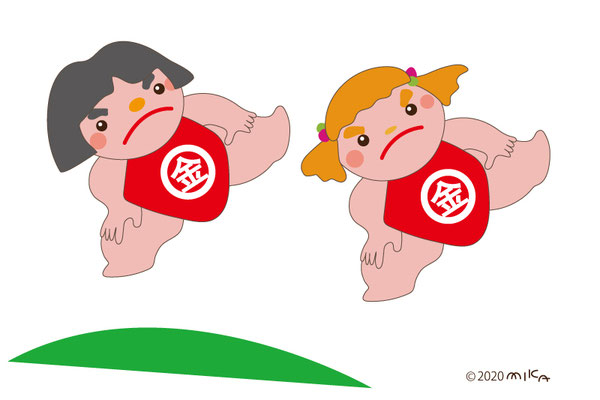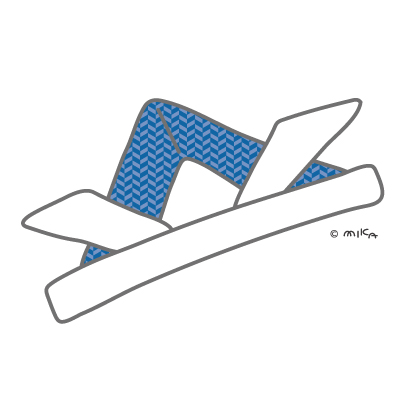- ホーム
- NEW
- ほっこりイラスト▼
- 季節の工作等▼
- ひと息 写真集▼
- 生き物図鑑▼
- 和みKANSAI▼
- 花と実図鑑▼
- 頭の体操
- 料理(ごはん)▼
- 月ごと絵手紙▼
端午の節句(こどもの日)
大きくなぁれ
・5月5日の「端午の節句」は男の子の節句。こいのぼりをあげたり、よろいかぶと等をかざったりするほか、ちまきやかしわもちを食べて、男の子が元気に成長することを祈ります。(女の子は3月3日の「桃の(上巳)の節句」)
・5月5日は「こどもの日」という祝日でもあります。端午の節句は男の子の行事ですが、「こどもの日」は、性別を問わず 子ども達のしあわせを祈る祝日です。
昔から中国には、コイが滝をのぼって、竜になるという伝説があり、この伝説が、日本で田の神様をむかえるための目印として、家の前に柱を立てる風習等と合わさり、こいのぼりを立てるようになったと言われています。
爽快な 吹き流し。5月が近づくと、各地でこいのぼりが あがります。
↑この写真は『こいのぼりフェスタ1000』芥川桜塚公園(大阪府高槻市)より。子どもたちが描いたかわいらしいこいのぼりが泳いでいます。
「かしわもち」と「ちまき」は、こども達の健やかな成長を願う和菓子。
かしわ餅の葉に使われる カシワの葉は、新芽が育つまで古い葉が落ちないため、子孫繁栄の願いがこもっています。↓
ちなみにクスノキも常緑樹として有名で、5月頃、古い葉の間から新しい葉が勢いよく伸びています。↓
※「ちまき」は米の粉で作ったおもちをササの葉などでくるんだ和菓子で、昔、中国の詩人、屈原(くつげん)が5月5日に亡くなったことをしのんで、ちまきをお供えしたことから、この日にちまきを食べる風習ができたとされています。
トイレットペーパーの芯で こいのぼりの工作
金太郎
「金太郎」は平安時代の武士、坂田金時の子どもの頃の名まえで、クマにのったり、まさかりをかついだりする姿が、おとぎばなしのモデルになっています。
5月5日の風景より
シバザクラの前で子どもに人気のキャラクターが置かれていました(ドラゴンボールと魔女の宅急便)
※イラストのみ再掲
※下記は別ページがあります
※ サイト内検索
このウェブサイトでは、快適な閲覧のために Cookie を使用しています。閲覧を続けることで、 Cookie ポリシーに同意したことになります。
本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。