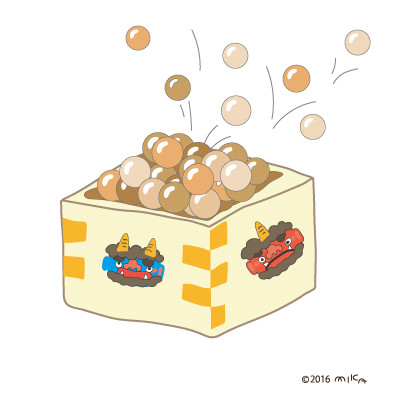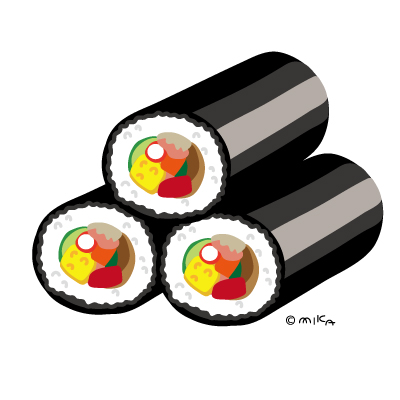- ホーム
- NEW
- ほっこりイラスト▼
- 季節の工作等▼
- ひと息 写真集▼
- 生き物図鑑▼
- 和みKANSAI▼
- 花と実図鑑▼
- 頭の体操
- 料理(ごはん)▼
- 月ごと絵手紙▼
節分(2月3日ごろ):冬と春の季節を分ける節目の日。むかしは立春、立夏、立秋、立冬の前日は、すべて節分と呼ばれていました。
豆まきや 恵方巻き(太巻きのまるかぶり)等、さまざまな行事や風習があります。
オニ(鬼)
オニは悪いことの象徴。十二支をあらわす方角の丑寅の方向に住むと言われ、おにの姿は、昔から ウシ(丑)の角と、トラ(寅)のきばをもち、トラの皮を着た姿で描かれています。
豆まき「福はうち」「鬼は外」
平安時代、豆には おにを追い払う力があるとされ、豆まきをしていたのが、江戸時代に一般に広まったと言われています。今でも 各地で節分にちなんだ行事が開かれています。
おたふく(お多福)
顔立ちが丸く、ほおが膨らみ、鼻が低めの ふくぶくしい顔立ち。昔から日本美人の典型とされてきました。 多くの福を呼ぶ顔の女性という意味から、「多福」になったとする説が有力とされています。
恵方巻
「恵方」は、その年の「十干(じっかん)」により、福徳をつかさどる歳徳神(としとくじん)のいる方向を「吉」の方向と定めたもの。
「十干」とは「 甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)」の事で、中国から伝わり、暦の表示などに用いられています。「恵方」は、この「十干」と東西南北の「四方」の組み合わせで決まり、基本的に、「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の四方向です。
十干による恵方は、西暦の1の位でも確認できます。西暦の1の位が「0,5」の年は「西南西」、「1,3,6,8」は「南南東」、「2,7」は「北北西」、「4,9」は「東北東」となっています。
たとえば、1の位が「4」の2024年の恵方は「東北東」、1の位が「5」の2025年の恵方は「西南西」等となります。
※以下は節分にちなんで、関西の節分祭、節分の工作等
※下記は別ページがあります
※ サイト内検索
このウェブサイトでは、快適な閲覧のために Cookie を使用しています。閲覧を続けることで、 Cookie ポリシーに同意したことになります。
本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。